中1の壁を越えるために
こんにちは。西東京市・東伏見駅から徒歩3分の学習塾、
「学び舎 子どものみかた」 の深松です。
小学校6年生も2学期が終わりに近づき、3学期はいよいよ中学校準備の3ヶ月になります。
小学校最後づくしで、寂しさと不安、ワクワクが混在している頃です。
冬期講習あたりから、中学生に向けて質問が増えてくるので、冬期講習前に少しお話ししようと思います。
中学1年生の1学期の中間テストが終わった頃、私は毎年のように、少し曇った表情の中学1年生と向き合うことになります。
「こんなに難しいと思わなかった」
「どこから勉強すればいいのか分からない」
「授業のスピードが早くてついていけない」
静かに、しかし確かに小さな声でつぶやく姿。それは決して珍しいものではありません。
世の中ではこの現象を 「中1の壁」 と呼びます。
これは単なる比喩ではなく、多くの子どもたちが実際にぶつかる現実の壁です。
◆なぜ「中1の壁」は起きるのか——20年続くデータが示すこと
「うちの子は大丈夫だろうか」
「中学校ってそんなに大変なの?」
保護者の方から、そんな声をいただくことがあります。
しかし、文部科学省の調査によれば、実際に 中学1年生の不登校者数は、小6の約3倍。
また、いじめの件数も小中を通じて中1が最も多いという傾向が、約20年間続いています。数字は淡々としていますが、その裏には、子どもたちが必死に変化へ向き合う姿があります。
では、何が子どもたちの心に負担をかけるのでしょうか。
◆原因① 勉強の仕方の変化——「自分で選ぶ」負荷が急に増える
小学校では1人の担任が1年間を通して寄り添ってくれます。
「分からなければすぐ聞ける」「何をするべきか事細かく説明され、分かりやすい」。
そんな環境に慣れてきた子どもたちが、中学校に入ると突然こう変わります。
- 教科ごとに先生が変わる
- 生徒に任され指示が大雑把になる
- 授業のスピードが速い
- 質問のタイミングがつかみづらい
- 宿題や提出物が一気に増える
- 定期テストで「まとまった範囲」が出る
この変化の大きさは想像以上です。
特に「どこを、どの順番で、どれだけやるのか」を自分で判断することに慣れていない子ほど、戸惑いやすくなります。
そして、分からない部分を自分で抱え込んでしまうと、授業が分からない → 勉強が嫌になる → さらに質問しにくくなる、という負のループにはまりがちです。
◆原因② 友人関係の変化——思春期の入り口で揺れる心
中学生になると、友達の作られ方が小学校と大きく変わります。
「席が近いから友達」「よく遊ぶから仲良し」という関係だけではなくなり、子どもたち自身が“価値観の合う相手”を求め始めます。
しかし、この時期はまだ自分の価値観そのものが揺らぎやすい時期。
・急に距離が生まれる
・ SNSのやりとりで気持ちが乱れる
・部活の先輩後輩関係に緊張する
・仲良しグループから外れたように感じる
こうした出来事が、子どもの心に大きな影響を与えます。
「友達に合わせなきゃ」
「言いたいことを言うと嫌われそう」
そんな不安の中で、無理をしてしまう子も少なくありません。
◆原因③ 生活リズムの乱れ——スマホ・部活・疲れの三重苦
中学生になると帰宅時間が遅くなり、部活も始まり、習い事や塾もあり、生活は一気に忙しくなります。
そしてスマホ・ゲーム・SNSといった誘惑も増えていきます。
・疲れているのにスマホを触り続けてしまう
・布団に入ってからもSNSを見てしまう
・夜更かしが続いて朝眠い
・集中力が下がり、授業が頭に入らない
この悪循環が続くと、勉強だけでなく人間関係のトラブルにもつながりやすくなります。
成長期の身体は、思っている以上に睡眠を必要とします。
けれど、子ども自身はそれに気づけません。
だからこそ、大人のサポートが必要なのです。
◆では、中1の壁をどう越えるのか
——「学び舎 子どものみかた」が大切にする3つの柱
子どもが一人でこの壁を越える必要はありません。
家庭・学校・塾、そして周りの大人たちが少しずつ関わるだけで、壁は驚くほど越えやすくなります。
◆① 家庭の生活リズムを整える
食事、睡眠、入浴、休息、団欒などの「流れ」を作っておくことは有益です。乱れがちな時こそ、型をなぞるように同じことをするのが落ち着きにつながったりします。
また、親子ゲンカの要因にもなりやすいスマホ。これについても、スマホの使い方を厳しく、子どもだけに課して、管理するのではなく、「家庭のルールとして、一緒に決める」 ことが大切です。
- 使う時間や場所を決める
- 寝る1時間前はスマホを見ない
- 充電場所をリビングにする
- 就寝・起床の時刻を固定する
- 生活習慣は時間ごとに決めず、「〜をやったら…をやる」の流れだけにする
などの工夫ができます。
ルールは「守らせるため」ではなく、家族みんなで子どもの未来のために一緒に守る という意識が大切です。
◆② 感情を言葉にして話せる家庭をつくる
友人関係の悩みほど、子どもは話したがらないものです。
だからこそ、大人がまず“感情を話す姿”を見せることが重要です。
「今日は仕事でこんなことがあってね、ちょっとイラっとしたんだ」
「あなたならどう思う?」
このように、感情を“共有する”習慣がある家庭では、
子どもは自然と心を開きやすくなります。
感情をぶつけるのではなく、
感情を言葉で表現する姿 を見せる。
それが、子どもが安心して悩みを話せる土壌になります。
また、親以外の第三者——祖父母、親戚、習い事の先生、信頼できる大人——がいることも、大きな助けとなります。
◆③ 勉強の「やり方」を身につける
中学生になったら、
勉強は「やり方」を身につける段階に入ります。
・授業中、分からないところに“?” をつける
・マンスリー手帳で、自分の予定を管理する
・テスト2週間前から計画を立てる
・小学生のうちから「まとめテスト形式」に慣れておく
・分からないところは溜めずにすぐ質問する
こうした習慣づくりは、大人のサポートが欠かせません。
家族は勉強を教えるのではなく、勉強習慣を身につけやすい環境作りに徹してほしいと思います。
当塾では、授業外でも質疑応答・学習相談に応じており、
子どもたちが安心して「分からない」と言える環境を何より大切にしています。
◆最後に——子どもの背中を、そっと支える存在でありたい
中1の壁は、
勉強・友人関係・生活リズムのすべてが変わる中で起こる自然な現象です。
だからこそ、
「できない自分」ではなく、「変化に向き合おうとしている自分」を認めてあげること。
それが、最初の一歩になります。
家族も、学校も、塾も。
そして私たち「子どものみかた」もまた、
そのまだ小さな背中をそっと支える存在でいたいと願っています。
もし今、お子さんの様子が少し気になっている方は、どうぞ一度ご相談ください。
一緒に、その子のペースで、この壁を越えるお手伝いができればと思っています。

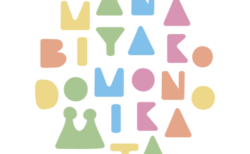




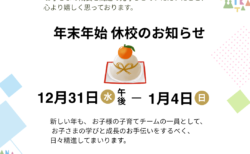

LEAVE A REPLY